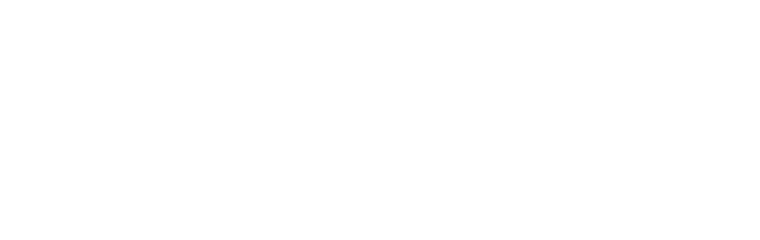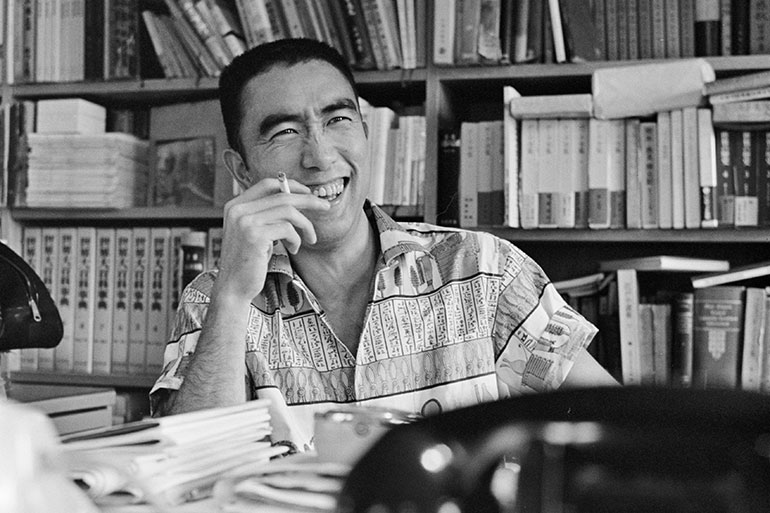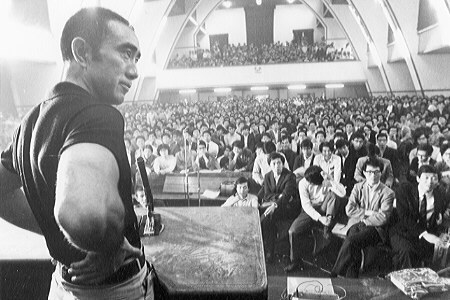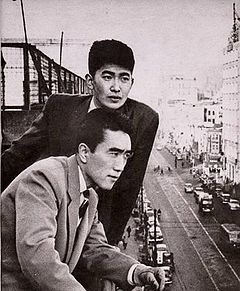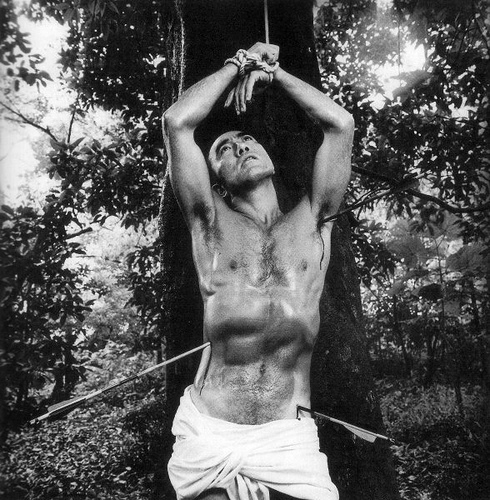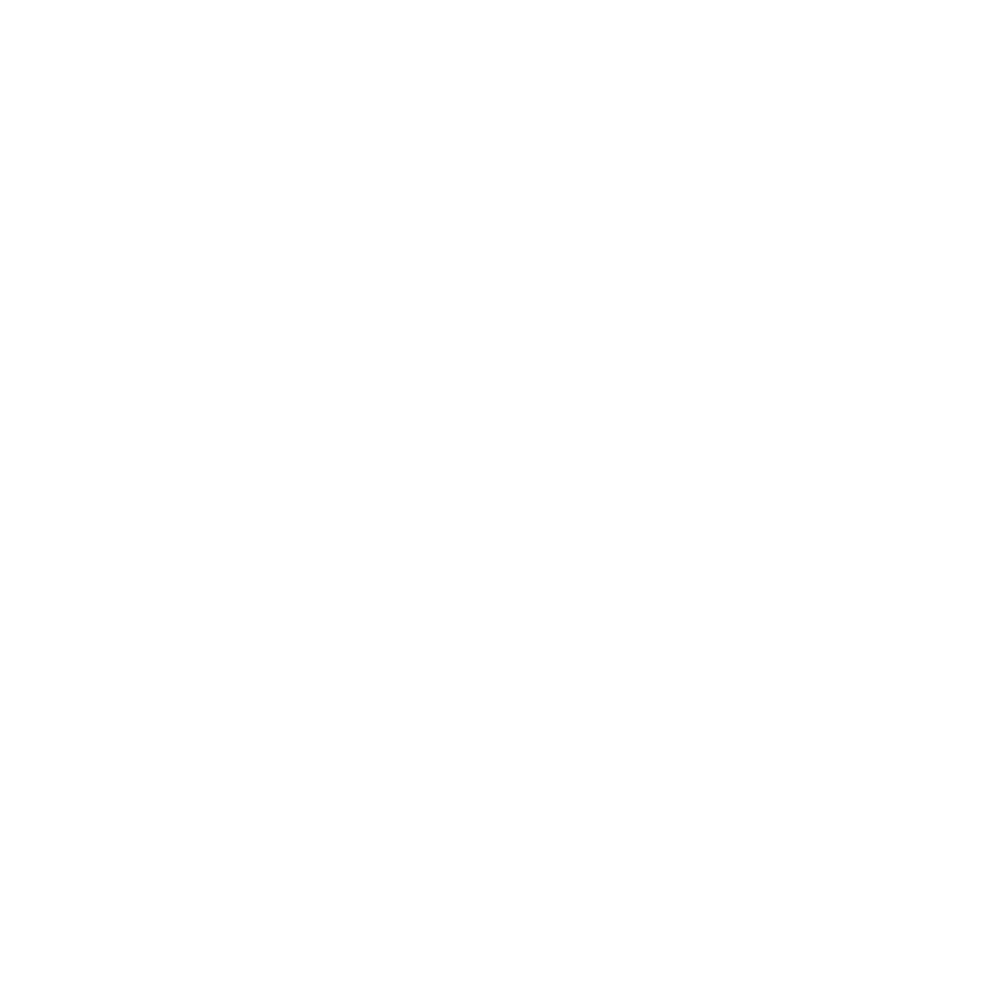新潮社版「ガルシア=マルケス全小説」の中の『落葉』を読んだ時の感想だが、これも残しておこう。
マコンドものの長編第一作だ。祖父、娘、孫の3人の視点、語りを通して、ひとりの男の死とマコンドの歴史が紡がれていく物語。3人の認識構造、語りによるポリフォニイ(多声)構造の小説が目指されているが、ぼくの見る限りポリフォニック効果に薄い。3人の語りがほとんどしりとりのような順番をたどっており、同じ言葉、同じ事実が3人によってほとんど同じ認識効果しかもたらされていない。この結果、語りによって言い回し、回想の歴史の深さはおのずと異なるが、3人のまったくちがう認識構造による現実の不可思議な再構成、ポリフォニイ小説という読後感がほとんどない。むしろ、あたかもモノローグの変形譚を読んでいるような気がしてくる。
本書解説によれば、このあたりはマルケス自身も認めていることで、複数人物によるポリフォニック効果を自在に駆使できるようになったのは、『族長の秋』以降とのことだ。大きく影響を受けていることが一読でわかるフォークナーの作品群『死の床に横たわりて』、『八月の光』、『響きと怒り』のポリフォニイ小説と比べてみれば、その多声効果のちがいは段違いだと思う。このため、フォークナーの「ヨクナパトーファ郡」とマルケスの「マコンド村」(『落葉』)とでは、中空に浮かぶ非現実性とでも呼ばれるべき小説世界の現実の幅の広さ、深さにおいて、フォークナーのほうがはるかに深く広い。「ヨクナパトーファ・サガ(神話)」と呼ばれる由縁である。
しかし、実はぼくの見る限り、マルケスの記憶さるべき点はここにはない。マルケスにあってフォークナーにないものは、伝承の強さである。伝承、民族の記憶、語り伝えが現実社会の根幹部分をつくっていく。この伝承、民族の記憶がマルケスには豊富であり、これらがマコンドの現実をつくり、作品の屋台骨となっている。これも本書解説によれば、マルケスは「現実に根ざさない言葉は私の小説には一行もない」と語っている。そのときの「現実」とはしばしば伝承であり、語り伝えである。少年時代のマルケスはその祖母から、「現実」としての伝承を豊富に語り聞かせられた。そこには幽霊をはじめとする民族の精神のありかと、その精神の織りなす「現実」があった。マルケスのマコンドもの、『落葉』や『百年の孤独』を読む者は、実はそこにポリフォニイを読んではいない。伝承、民族の記憶が形作っていくある社会の現実のダイナミクスを読んでいる。
余談だが、ぼくの少年時代、ぼくの母方の祖母からしばしば不思議な話を聞いた。その記憶のうち、いまだに不思議な「現実」の記憶として残っているのは、次のような話である。ほとんど夜に近いある夕刻、少女時代のその祖母は村のはずれの森の上に橙色にぼんやりと光る大きな物体を目撃したという。目撃者はその少女だけではなく、その近辺の人々みなが同じものを見、騒然となったという。ぼくはこの話を聞いたとき、この話はまぎれもなく「現実」にあった話だと確信した。この話には、実は「橙色にぼんやりと光る大きな物体」をめぐる物語が欠けているのだが、マルケスが聞かされた伝承には、そこに豊饒な物語と歴史が刻まれていたことだろう。
しかし、このことをひるがえって考えてみれば、返す返すも残念なことである。ぼく自身、その伝承の物語の記憶はない。現在、伝承を語ることのできる人物はおそらく皆無に近いのではないだろうか。民俗学者の仕事をたずねることはきわめて重要であり、楽しいことではあるが、自身にその記憶が薄いということはやはりさびしすぎる。
この新潮社版「ガルシア=マルケス全小説」には短編集『青い犬の目』に含まれた、マルケス20歳代の短編なども入っているが、これらは意外におもしろい。当然のことながら作家の卵としてのマルケスには様々な可能性の方向があったと思われるが、修練を積むうちに選び取っていった道は、伝承と民族の記憶が形作る「現実」の歴史物語、マコンド村であった。