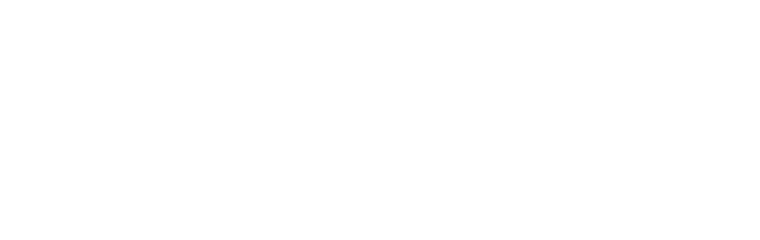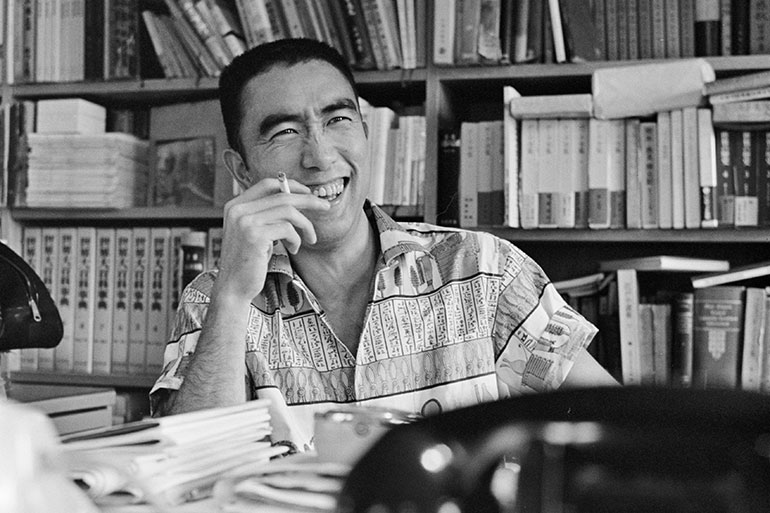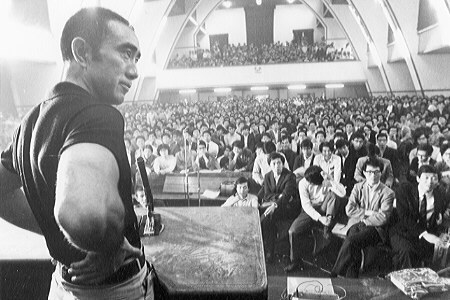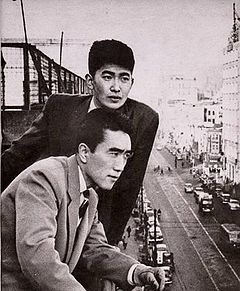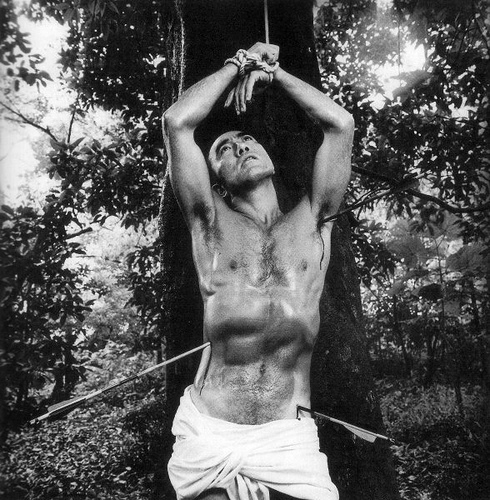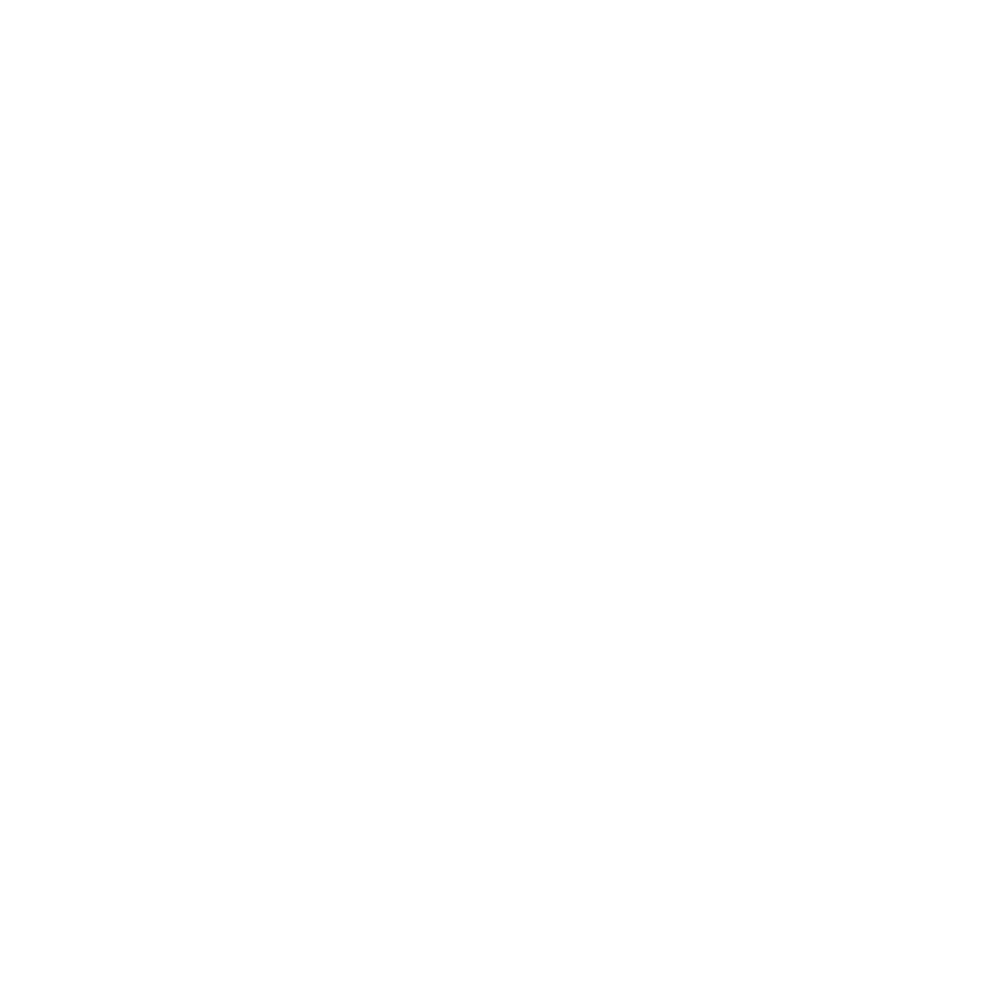ボルヘス的心象風景とでも呼んだらいいのか、あるいは単に言語論的思い出といったほうがいいのか。どちらにしても不思議な記憶がある。大体この文章自体16年前のものだが、ぼくの名前ではどこにも発表していないので、この際残しておこうと思う。
都の西北に位置するある大学に通っていた学生時代、漠然と小説家にでもなってやろうと思っていたぼくは、同じサークルに所属する飲み仲間Yと同人誌をつくっていた。Yは生涯の親友・悪友だが、この記事とは関係がないのでここではこれ以上触れない。そのころのぼくの文学上の最大関心事の一つはサルトルを中心とする実存主義と、バルト、ソシュールから学んだ言語論だった。
同人誌の中で、ぼくはある実験小説を書いた。言語論の中では知られた「入れ子体系」、あるいは「コノテーション」の考え方をひとつの構造にした恋愛小説だった。もちろん、下地には牧野信一の「西瓜食う人」などという小説も頭にはあった。読者に受けるかどうかなどということは一切無視してぼくはこの手法、構造を実験小説の中で追求してみた。おそらくはただの自己満足に過ぎない、きわめて難解なしろものができあがった。改行なしで100枚程度。恋愛関係に陥った男女が、次々に相手の認識構造を包み込んで、めくるめく入れ子構造の中に読者を誘い込むという体のもので、完成作を前にぼくはひとり悦に入っていた。
ある有名な文芸雑誌の同人誌評で取り上げられた。しかし、その批評家は「きわめて異端。私にはベケットより難解だと思われた」と評した。受けを狙ったわけではなかったが、世間的にはその実験作はそれで終わった。
しかし、ぼくの中ではそれで終わったわけではなかった。ある日、同じサークルに所属する学生が、ぼくに会いたいという高校時代の友人がいるので会ってやってほしい、ということを言ってきた。ぼくに会いたいというその学生は、ぼくの作品を読んで関心を持ったとのことだった。某日、ぼくは武蔵野のキャンパス内に建てられたその寮に出かけてみた。その学生の部屋に入り会話を交わすうちに、ぼくはその彼に完全に敗北したことを悟った。部屋の壁にはサルトルをはじめとする実存主義者の言葉がフランス語のまま貼られ、その学生の言葉は、そのときのぼくが思うに完全に哲学者のそれであった。彼の考え方、推測される膨大な読書遍歴に圧倒される不思議な夜だった。
それから20年近い歳月が過ぎたある夜、ぼくは著名なA賞を受賞した若手現代作家Oの代表作を読んでいた。その翌日、視聴者の受信料で運営されている某テレビ局の求めに応じて、その作家とテレビカメラの前で対談しなければならない羽目に陥って、急遽その作品を読んでいたところだった。といっても、ぼくがジャーナリストとして特別な記事を書いたとか偉大な思想を語ったとかということではまったくなかった。
その以前にぼくはロシアに取材旅行に出かけ、『ドストエフスキーの黙示録』という本を出していた。この仕事がテレビ局ディレクターの目に止まり、その現代作家Oの対談相手にちょうどよいと思われただけのことだった。
ソファに横たわりながらOの小説を読んでいたぼくは、徐々に不思議な感覚と暗合の小世界に引き込まれていった。その作品は、きわめて洗練されていたとはいえ、若い男女の恋愛を「入れ子体系」の構造の中に組み込んだものだった。「同じ構造だな」と思いながら、ぼくはある種の興奮を味わった。
ところが、あるところにきて、ぼくは思わず身を起こした。「入れ子体系」の中で、主人公の学生のアルテルエゴ、つまり分身を務めるもうひとりの学生の出身が、都の西北に位置する大学だった。
ぼくは、その作家の経歴にあらためて目を通してみた。すると、ある驚きがぼくを痛撃した。武蔵野にキャンパスを広げる大学の出身だった。しかし、作家Oは、ぼくが学生のときに会った「哲学者」学生ではないことはわかり切っていた。
撮影の当日、打ち合わせのときにぼくは、自分も学生時代に言語学的な考え方を下敷きにした実験小説を書いたことがあるということを遠まわしに伝え、「哲学者」学生のことを聞いてみた。すると、作家Oは、その「哲学者」学生は同じ文学仲間であり、現在もアルバイトをしながら同じような「哲学生活」を続けているということを話した。作家はもちろん牧野信一を読んでおり、ぼくの推測通り、その作品の主人公の名前は牧野の小説からヒントを得てつけたものだった。
ぼくは、学生時代の自分の作品との共通性などというものをその作家に言うことは避けた。隣にはディレクターが座っているし、当然ながらそれが礼儀というものだろう。その作家とぼく、いまだに「哲学生活」を続けている元学生の3人の年齢はたしか同じだった。
作家Oは、もうひとりの武蔵野生の影響を受けて、学生時代にぼくの実験小説を読んでいたのかもしれないし、そうではないのかもしれない。バルトやソシュールに強い関心を持って愛読し、その言語論を小説の構造に応用してやろうと考えること自体は、ある意味でその時代の文学を学ぶ者の一つの必然であり、その者同士が後年邂逅することは一つの偶然のなせるわざだろう。そして、そのこと自体はどちらでもいいような気がする。
結局は、同じ時代に文学や哲学を志した複数の学生が別の場所で同じような読書体験をして、同じようなことを考えていたということだろう。
しかし、それにしてもぼくがある意味で懸命に読んで学び、ある意味で時代の最先端だと密かに己惚れていた実験作の構造が、より洗練された形でよりドラマチックに展開され、この国最大の文学賞を見事に受賞した姿を目撃して、何とも言えない深い感慨に囚われた。
「ボードレールの影には100人の無名のボードレールがいた」というようなことを言ったのは小林秀雄だったような気がしたのだが、検索してみても一向に出てこなかった。だが、ぼくの味わった感慨はこの言葉の中にも含まれているような気がする。