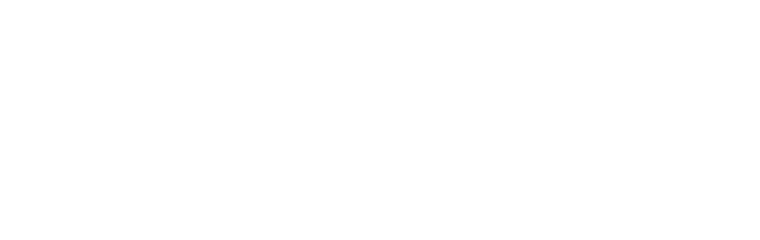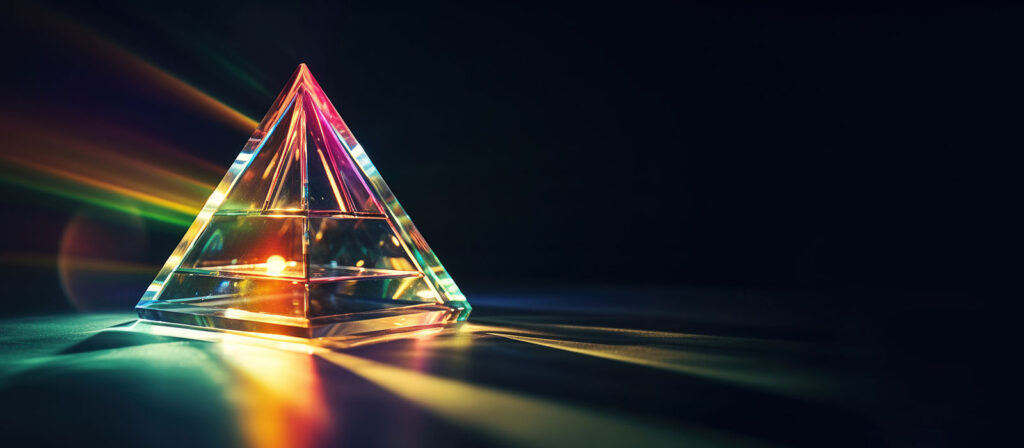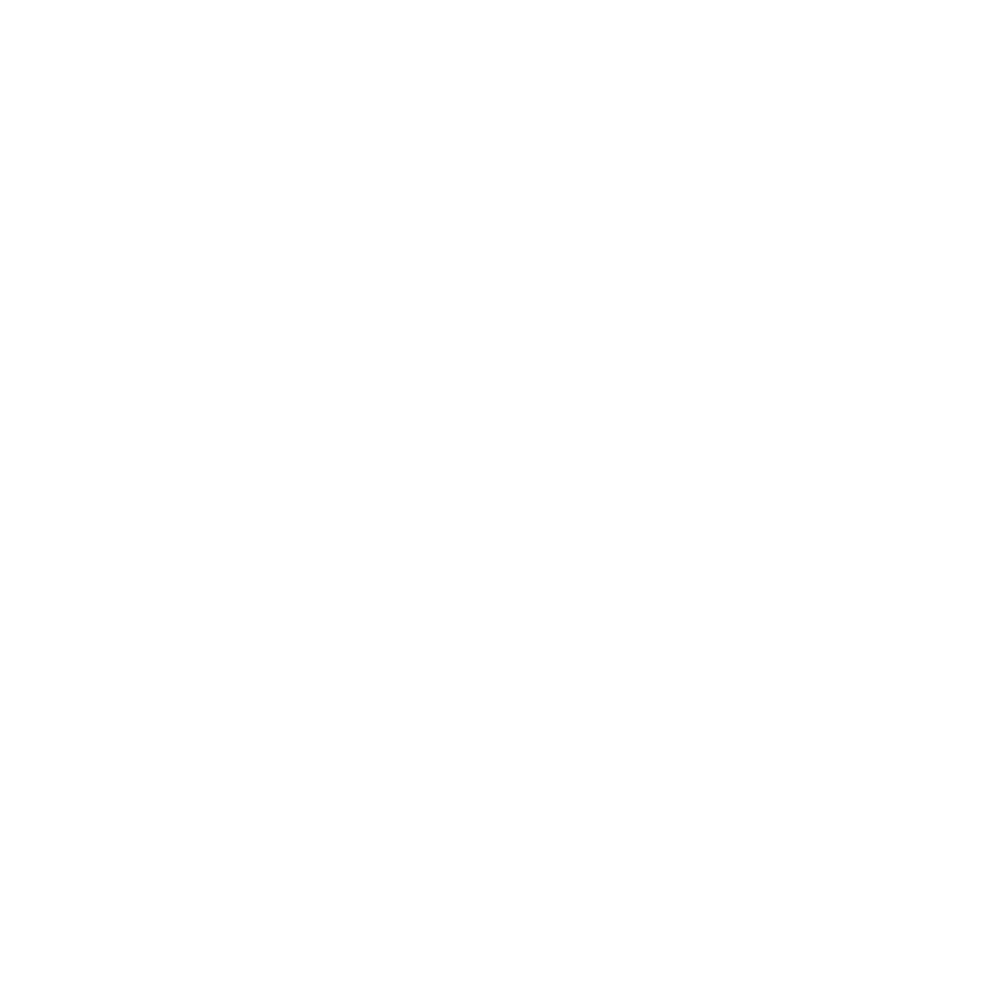簡単な経歴は「プロフィール」に記した通りだが、ジャーナリストとしての自分自身をもう少し深く理解してもらおうと思えば、やはり経歴を照射する光を屈折させる自分自身の「プリズム」を利用せざるをえない。
ぼく自身の「プリズム」を通してぼくの経歴に光をあてた場合、まずはぼくの学生時代が浮かび上がってくる。ぼくは早稲田大学政経学部の政治学科卒業だが、政治学に特別に身を入れて勉強をした記憶がない。教授が挙げる参考文献や教科書を読んだりはしたが、そのような本よりも打ち込んで読み耽ったのは世界文学であり、実存主義をはじめとする哲学書であった。
ウイリアム・フォークナー『アブサロム、アブサロム!』の終わり近くに黒人の老婆の頬を転がり落ちていく熱い涙。ジャン・ポール・サルトル『自由への道』でマチュウが自分の手のひらにナイフを突き立てる。そして、ドストエフスキー『罪と罰』の主人公ラスコーリニコフがひとりの娼婦の前にひれ伏してその汚い足に口づけをする。「いまお前の足に口づけしたのではない。全人類のこれまでのすべての苦難に対して口づけしたのだ」とラスコーリニコフ。
きしみ続ける世界と現代史の中で翻弄され挟撃され続ける人間たちの悲痛な声を聴き、サルトル『シチュアシオン』に目を走らせた後、大学の教室でノートを開いてもメモを取ろうという気持ちが起きなかった。
朝日新聞社はぼくのような劣等生をよく採用してくれたものだと思うが、地方支局での取材経験は、学生時代に育まれたであろうぼくの志向性をより強固なものにしてくれた。「プロフィール」では省いたが、水戸支局に3年8か月、山形支局に1年4か月在籍した。
初めて新聞記者となって警察を担当した2年間、交通事故から各種犯罪、大事件、大水害などに振り回され、日常的に人の「死」に直面することになった。交通事故で人が亡くなった場合、必ず顔写真を手に入れなければならない。どのように入手するのか。遺族の家を訪れ、御焼香を差し上げることを申し上げ、長い時間故人の思い出話に耳を傾ける。そして最後に故人の顔写真の接写をお願いする。
この仕事が特に辛いのは子どもが犠牲となった時だ。子どもが犠牲となるのは交通事故と並んで夏の川遊びでの水難事故がかなり多い。子どもを助けようとして犠牲となってしまった母親の事例も取材した。残された遺族の悲痛は言葉にすることができない。
ぼくは、水難事故を防ぐための記事などを書いたが、子どもの水難事故と聞くと体が熱くなるのを感じる。一報を聞いて車で現場に急行する時、現実的にはありえないのだが「今おれが助けてやる」という焦りとはやりの気持ちを抑えることができない。
こういう気持ちや感情のうねりは水難事故や交通事故に対するものだけではなかった。町長レベルの汚職事件はいくつも経験したが、たとえ小さい町の町長であっても住民や町の業者から見上げた場合、いかに大きい存在であるかということを実感して何とも複雑な感情を味わった。霞ヶ浦の浚渫工事を舞台にした大きい談合事件も取材した。公共工事をめぐって土建業者と県当局がいかに深く結びついているかということを実感をもって知ることができた。
この人間社会で綺麗ごとは通用しない。いや、綺麗ごと自体この人間社会には存在しないのではないか。あったとしても極めて稀な存在だろう。この人間社会に存在するのは悲痛な出来事と儲け話、あるいは権力者の支配と被支配、その支配関係を覆すような裏切りと反逆だけだ。ぼくは、水戸支局で経験した2年間の激しい警察担当期間を含めた5年間の地方支局時代にそのような理解に達した。そして、その理解は、ぼくが学生時代に親しく学んだ世界文学や実存主義哲学の書が繰り広げていた世界観とかなり通底するものだったと思う。
地方支局から東京本社の経済部に上がり、まず日銀の記者クラブに入って金融経済を学んだ。大蔵省(現財務省)の記者クラブ「財政研究会」に所属し、政治と経済の接点を観察した。ニュース週刊誌と銘打った「アエラ」に移り、政治家との接点が広がった。そのころに出版した『ドキュメント金融破綻』(岩波書店)や「アエラ」の記事が読まれ、政権交代前の民主党有力政治家から協力を要請された。
ぼくは、協力する代わりに一つの条件を出した。大蔵省が持っていた財政政策部局と金融政策部局を解体させることだった。結局、歴史的には大蔵省から金融部局が独立して金融庁となったが、ぼくはさらに財政政策そのものを政治の側が取り戻すことを考えていた。もちろん、ぼく自身だけが考え付いたわけではない。この当時の少なからぬ政治学者、日本政治研究者はそう考えていた。本来は、マクロの財政政策は国民から選ばれた政治家が国民の負託を得て展開しなければならない。だが現実には、自民党政治家は長年、自分の選挙区に公共事業を持ってくることだけに専心し、本来のマクロ財政政策、経済政策は大蔵省に全面的に任せきっていた。これでは、国民の生活に顔を向けた本来の財政政策、経済政策はできない。
しかし、その後政権党となった民主党は、財政・金融分離は成し遂げたが、政権党が財政政策を取り戻すという大きい使命を果たすことに失敗した。このことの経緯はぼくの著書の一つである『職業政治家 小沢一郎』(朝日新聞出版)に詳しく書いたが、肝心な部分を簡単に記しておけば、この大きい使命を背負った国家戦略局が完全に失敗に終わってしまったからである。そして、国家戦略局の完全失敗が民主党政権崩壊の最大の要因となった。
ぼくは果たして、ここで何を言いたいのか。
「この人間社会に存在するのは悲痛な出来事と儲け話、あるいは権力者の支配と被支配、その支配関係を覆すような裏切りと反逆だけだ」ということが人間社会に対する基本理解だとすれば、この人間社会の進む方向を少しでもまともな方に向けるためには、この人間社会を形作る政治の構造を変えていくしかない。現在の日本の政治構造は、明らかに合理的なものではない。少なくとも日本国民が第一に考える政治選択が優先される政治構造ではない。
政治と社会、宗教を考える時、ぼくの念頭にいつも浮かぶ言葉がある。
――人間の行為を直接に支配するものは、利害関心であって理念ではない。しかし、「理念」によってつくりだされた「世界像」は、きわめてしばしば転轍手として軌道を決定し、そしてその軌道の上を利害のダイナミックスが人間の行為を推し進めてきたのである。(マックス・ウェーバー『世界宗教の経済倫理・序論』)
もちろん、これはキリスト教やイスラム教、仏教などの世界宗教が歴史的に形作ってきたその社会の「理念」や「世界像」のことを言っているものだが、現代社会において形作られる「理念」や「世界像」は必ずしも世界宗教だけに限られたものではないのではないか。特に現代日本の場合、社会の軌道を決定する「転轍手」は仏教であるよりも何か他のものであるだろう。
いまそれを明示的に名指すことはできないが、少なくともそれを考えようとすることはできる。そして、それを考えることによって、あるいは考えること自体が時代の「転轍手」を現出させることになるのではないだろうか。